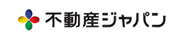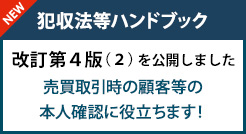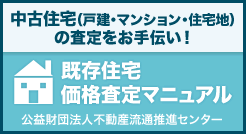※入力項目は全て必須入力です。
◆更新者の情報
氏名
メールアドレス ※解答をお送りしますので、お間違いないようご確認ください。
更新手数料の振込名義 ※会社名等でお振込みされた場合はその名義をご入力ください。
◆確認事項(誓約書)
◆法令改正のポイント 小テスト
「平成30年度版 法令改正のポイント」を読み、以下の記述について○か×で、解答せよ。
◆更新課題
(この問題は、第2回宅建マイスター認定試験をアレンジしたものです。)
宅建マイスターである甲宅地建物取引士(以下、「甲宅建マイスター」という。)は、永田一郎氏から「親から相続で譲り受けた中古住宅とその敷地(以下、「対象不動産」という。)を6ヶ月以内に売却したい。」との依頼(以下、「本件取引」という。)を受けた。
本件取引の調査を担当する乙宅地建物取引士(以下、「乙取引士」という。)による報告内容は、【別紙】「対象不動産の概要及び物件調査報告」(以下、「調査報告」という。)に記載されたとおりである。
 【別紙】「対象不動産の概要及び物件調査報告」
【別紙】「対象不動産の概要及び物件調査報告」
こちらをクリックして表示してください。
調査報告をもとに、乙取引士が指摘した本件取引における留意事項及び想定されるリスクは、以下1.のとおりである。
乙取引士が指摘した留意事項に関する、下記の【問1】に答えなさい。
1.乙取引士の指摘した留意事項など
(1)敷地内の水道管とガス管がいずれも東側隣地(地番509番2)と共用管である(売主から聴取)ことから、再建築時には、既存の水道管及びガス管の引込み直しについて、隣地所有者との交渉が必要となる。
(2)平成20年から対象不動産の地域は公共下水道の供用開始区域となっているが、「建築計画概要書」では浄化槽を使用している。
(3)北側隣地地番511番の所有者が行方不明であり、境界確定できない可能性がある。
→ このままでは、隣地地番511番の所有者との立会いが困難であり、境界を確定するには、所有者を通じて司法書士へ所有者調査の依頼が必要である。さらに場合によっては、[ A ]制度の活用も検討する必要がある。
報告を受けた甲宅建マイスターは、本件取引を進めるにあたり、乙取引士の調査報告をもとに、さらに留意すべき「内在するリスク」(※)及びその調査について以下2.のとおり指摘した。
※「内在するリスク」とは、表面的に現れてはいないが、調査によって知り得た情報を論理的に組み立てることで類推することができるリスクのことを言います。
甲宅建マイスターが指摘した事項に関する、以下の各問に答えなさい。
2.甲宅建マイスターが指摘した事項
(1)相続人である所有者は、排水設備の状況について承知していないが、まず、「浄化槽点検記録の書類」(浄化槽法8条~10条)が保存されていないか、所有者に確認してもらう必要がある。また、公共下水の供用開始に伴い浄化槽使用から公共下水道へ切り替えている可能性も否定できないため、役所にて、公共下水道への接続の状況や「浄化槽廃止届」(浄化槽法11条の2)の記録の有無等を確認する必要がある。
公共下水道に切り替えられていた場合は、以下の調査が必要である。
追加調査の内容
・現地の状況の確認
・公共下水道に切り替えの際の、工事請負書類の有無と内容の確認
・試掘による確認と費用見積もり
(2)また、地番498番3他の土地上にある「ABC工業」は工場として稼働しており、乙取引士のヒアリングにより、現在は暗渠になっている用悪水路(公図及び写真5、6)を工場排水の排出先として利用していたと推測される。
公図及び現地状況(写真3、4)をみると、対象不動産の前面には用悪水路としての地番は確認されず、外形上暗渠の有無は不明であるが、さらに詳しい調査が必要である。