サイト内検索
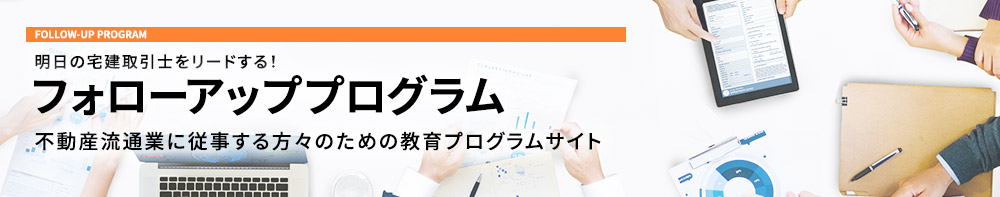
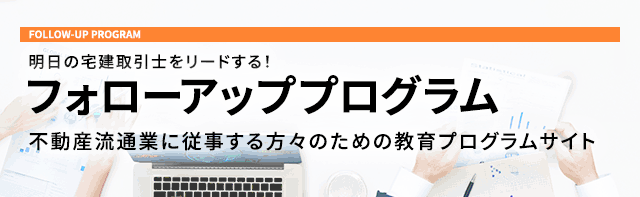
フォローアッププログラムサイトは、2025年3月31日をもって終了となりました。
なお、当センターが実施する講座・研修・試験等の情報提供を希望される場合は、「メールアドレス登録フォーム」よりご登録ください。
※フォローアッププログラムサイトにご登録済みの方には、引き続き今後も研修等のご案内をお届けしますので、あらためてのご登録は不要です。
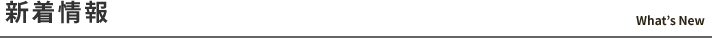 新着情報
新着情報 フォローアップカレッジ2024
フォローアップカレッジ2024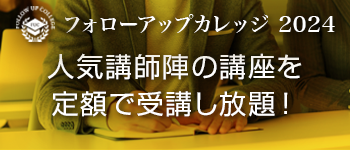
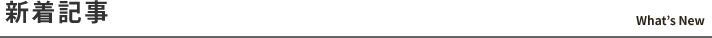 新着記事
新着記事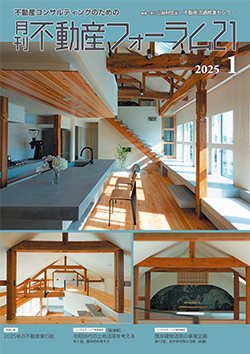
2025.04.22掲載 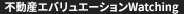
間取り表記をカフェとしたのは珈琲を愉しむ空間を目指したから… それは味や香りはもちろん淹れる過程から五感で感じること そこは空を眺め、抜ける風や光を感じ余計な...

2025.03.24掲載 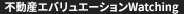
「元のお家にあった意匠は、どこまで残す?」。格子や梁などは、うまく残してリノベーション後も空間の“顔” となることが多いですが、では、「欄間」についてはどうでしょ...
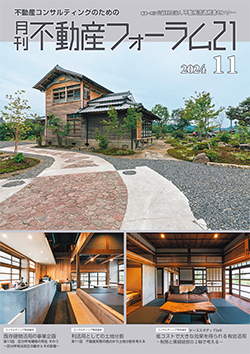
2025.03.13掲載 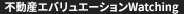
まずは、建物に入れないほど鬱蒼とした草木の伐採からこのリノベーションは始まった。 仕事の合間を縫って数ヶ月かけて伐採すると、かつて大地主の家であった伝統様式の詰...
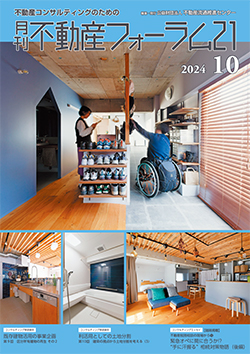
2025.01.14掲載 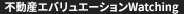
学生時代に交通事故に遭い、車椅子生活を余儀なくされたお施主様のための住まい。 以前の住まいでは、引き戸で段差のない賃貸でも洗面台では上体を捻り、換気扇はマジック...

2024.12.09掲載 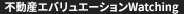
古い家屋を解体した後、捨てられてしまう古材をリノベーションで再利用しました。リビングドア・トイレドア・廊下収納の扉・洋室のクロゼット引き戸・キッチン腰壁の組子は谷...