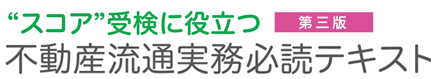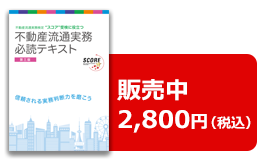他人の私道の通行等を前提にしている宅地は頻繁にみられます。私道等の所有者との間で、通行等の同意や上下水道やガス配管の設備新設のための掘削同意をめぐり紛争になる場合もあることから、権利関係の有無については、細心の調査が必要です。

目次
他人の私道の通行とは?
人格権に基づく通行権とは?

私道の権利に関するトラブル事例
【 概 要 】
①買主甲は、宅地建物取引業者丙の媒介で、売主乙から中古の土地付建物を買い受ける旨の売買契約を締結し、代金全額を支払って、引渡しを受けた。
②本件敷地の前面の第42条第2項道路は実は車で乗り入れできる側は公道に接しておらず、公道と前面の2項道路との間に隣接者の私有地が存在していたが、事前には不明であった。
③甲は、購入した建物が古家であったため、これを解体し、新築の家を建てることとして、古家を解体した。
④甲は、請負業者と工事請負契約書を締結し、地鎮祭を行ったが、その際近隣者丁に挨拶に行ったところ、丁は、「解体時に挨拶がなかった。今頃挨拶に来て、この道路が通れると思ったら大きな間違いだ」と言われた。
⑤甲は、丙に調査してもらったところ、②の事情が判明した。
⑥丁は、同年10月、私有地にインターロッキングの舗装をし、地面には埋め込み式のセンターポールを設置するなどして車両通行ができないようにし、説得は不調に終わった。
< 問題点>
物件売買の仲介をした宅地建物取引業者丙は、本物件の重要事項説明に際し、区役所に行き、本物件の前面道路が建築基準法第42 条第2項道路による道路であることは調査したが、直近の公道に通じているか否かまでは調査しなかった。
私道の権利に関する出題例 (スコア第7回 設問14 正答率71%)
私道における民法上の権利関係に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい
1.私道の所有者は、第三者に通行権を設定している場合でも、これを自由に廃止することができる。
2.私道の通行権を有している者であっても、その私道が第三者に譲渡された場合、新しい私道の所有者に対して通行権を対抗できないことがある。
3.通行地役権は物権的な強い権利であるため、契約書のない口頭の合意や時効により成立することはない。
4.他人と共有している私道の舗装を補修する工事をする場合には、共有者全員の同意を得る必要がある。
解説
●問題のねらい
私道について、民法上の権利関係についての理解を問う問題です。私道の通行権といえども、民法上、通行地役権、囲繞地通行権、債権的通行権など多様な 権利構成が想定されます。他方、私道の通行権の設定については、契約書が存在しないことも多く、いずれの通行権が成立しているかは法的判断を経て決される場合があります。
また私道は共有されていることも多いため、共有に係る法律関係の理解も重要です。
答え:2
1.不適切
建物の所有者が賃貸している建物を、賃借人の承諾なく取り壊すことができないのと同様に、私道を開設し第三者に通行権を設定した場合には、私道の所有者といえども、私道を廃止することはできないことがあります。
2.適切
通行権といえども、物権的な通行権については、対抗要件を備えている場合等には、当該私道の譲受人に対しても対抗可能な場合が多いです。しかし、単なる契約上の債権的通行権に過ぎない場合には、当該私道の譲受人に対して通行権を対抗できない場合があります。
3.不適切
通行地役権は、黙示的合意により成立が認められる場合や取得時効により成立する場合があり、地役権の設定契約書が存在しているとは限りません。
4.不適切
共有者は、他の共有者の同意なく、当該共有物の保存行為を行うことができます
(民法第252条ただし書)。それゆえ、例えば、私道の舗装が劣化しており補修が必要な場合等には、他の共有者の同意なく、補修工事を行うことができます。
他人の私道・掘削同意に関する実務のポイント
○ 媒介業者は買主に対し私道特有の問題点を調査・説明する必要があります。
1.私道の持分があるか否か?ある場合は共有持分か分有か?
分有の場合の問題点は?持分がない場合の問題点は?
2.上下水管、ガス管等の配管が公設配管なのか私設配管なのか?
私設配管の場合は、将来リニューアルする時には、私道所有者全員の同意と費用負担が必要となること。また、道路の掘削、舗装も同様であること。
3.持分が共有であったり、持分がない場合、現在、私道に障害物がなくても、将来ポール等の障害物が設置される可能性があること。また、その障害物を撤去させることが困難であること。
4.対象私道に道路交通法の適用があるか否か? 同法の適用がない場合、第三者が私道上に車を駐車、放置しても、警察の取り締まりの対象とならないため、車を移動させることができないこと。
○「当然に無償で通行できるものではない」という認識を持ちましょう。
売主が今まで無償で通行できていたとしても、買主も同様に通行できるとは限りません。
○売主と私道所有者の人間関係によっては、私道の通行や掘削同意に関してトラブルが生じることも多々あります。私道所有者の人となりや、近隣住民との人間関係については、売主から十分ヒアリングするようにしましょう。